入り婿、婿養子って、現代から見てどうなのでしょうか、歴史的に普通にあったことなんですよね。
これはもう歴史になるかなと思うのですが、日本では家を継ぐために、入り婿に入る習慣がありますよね。
男性としては、名字が変わることと、家付き娘(たいてい財産付き)と結婚することで、なんかミエミエのお金目当てと思われるでしょうか、マスオさんとしてわりきっちゃうでしょうか。
でも、これは江戸時代の名残りなんですね。
江戸時代の武士の家は、簡単に財産を分けて分家することが出来なかった、女子が家を継ぐことが出来なかったために考え出された制度ですね。
なにせ家さえあれば石高(お米=収入)が付いてくるので、男の子が何人もいる家では、長男以外の次男、三男、四男、五男が、女の子しかいない家に入り婿に入って跡を継ぐのは、普通のことだったんです。
ちなみに、肺炎や結核、天然痘とかはしかで若くしてあっけなく亡くなる人が多いために、女性が未亡人になったり、男性がやもめになることも多く、再婚とか当然で、何度も結婚する人は多かったんですよ。
女大学という江戸時代中期以降にあった教訓書に、二夫にまみえず(結婚は一度だけ)とあるために、離婚再婚は最近のことだと思われているんですが、なんの、昔の方が多かったのは確かです。というわけで、明治や大正、昭和になっても、そういう習慣で家と財産、その存続を大事にするために、婿養子は行われていたんですよね。
有名な人で言えば、斎藤茂吉、湯川秀樹(父は京大教授で5人兄弟すべて学者、そのうち2人が婿養子に)がすぐ思い浮かびます。
じつは、前に「カイヘイのオッサン」という、ハタ迷惑な親戚のおっさんの言動を書かせていただいたのですが、このカイヘイのオッサンに、私の祖父が婿養子であることをあれこれ言われたことがあるんです。
オッサンは、「(祖父の家は)貧乏だったのか」と聞くんですね。
え?と絶句した私にオッサンは、「米ぬか3合あれば、養子に行くなというじゃないか、金がなかったんか」と言いました。
それは、ほいほい養子に行くな、苦労するぞといういましめの言葉だと知っていましたが、オッサンのあまりのもの知らずに加えて、祖父の実家を貧乏な家と決めつけてどうする、昔のことをよく知らない私に聞いて答えられないといじめてんのかよと、言葉を失ってしまいました。
私の祖父については、オッサンは私の両親の結婚前からどういう人か知っているし、はっきりいって存命中は側にも寄れなかったはず(ちょっと偉い人だった)、そこまで貶めたい理由は何だと母に聞いても首をかしげるばかりでした。
母はしかし、カイヘイのオッサンの祖父も婿養子だったのに、何言ってんだあいつはと言い放ちました。
天に唾するってこういうことかもしれないです。
祖父の父は蘭学医だったということで、○○に勉強に行った、名簿を見たら載っていたと父が言っているのを聞いた覚えがあるんです。
地理的に言って適塾だろうと思うのですが、今後時間が出来たら先祖調べをしてみたいものです。
ただ、祖父の父も婿養子なので、調べるの難しいかもしれないですけどね。
※画像はイメージです。
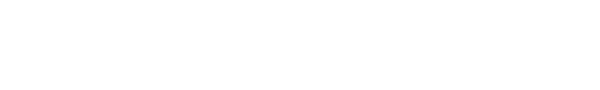


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!