世界各国の文化や伝統を冠婚葬祭に着目して比較する機会があり、その際に興味深いと感じた「泣き屋」という職業。
一体どんな職業か、この職業の存在意義から見えてくる各国の「死」の捉え方に焦点を当て考えてみようと思う。
泣き屋とは
一文で表すなら「葬儀の際に呼ばれ共に参列し、その場で号泣する事を生業としている人」のこと。地域によっては「泣き女」「哭き女」ともいわれ、この別称から泣き屋の比率は女性が多いと推測される。
泣き屋の泣くさまはとにかく激しい。故人との別れを前にした時の「辛い」「悲しい」「やるせない」そんな感情を泣きじゃくる事で表現する。時に吠えるように泣き、内に溜まった感情を発散するように地面を転げ回る。何なら故人と見知った間柄の配偶者や親族たちよりも激しく泣き喚く。
深く調べると、葬儀に呼ぶ人数や細かいオプションも選択可能。報酬も伴って変動し、あの泣きじゃくる姿がただがむしゃらに泣いているだけでない、プロが技を見せている姿なのだと思い直させられる。
世界に散見する泣き屋
驚くことに泣き屋は今なお世界各地に存在する。アジア地方で散見する泣き屋は遡ればエジプトやヨーロッパ地方にも文献が残っており、なんとかつての日本にも泣き屋を呼ぶ旧習が存在していた。
近しくは戦前、習慣の文献がある地方としては南は琉球北はアイヌと幅広く旧習も泣き屋も存在していたようだ。
弔いの場における泣き屋の存在意義
世界各国に根付く死の概念、弔いの作法は軒並みバラバラなので、葬儀の場に泣き屋を呼ぶ理由も各国でバラバラだ。
例えば日本では泣き屋は神話の中にすでに描かれている職業で、泣き屋の涙に「悪霊を退ける」あるいは「故人の魂を呼び寄せる」などの意味を持たせた。対して中国やヨーロッパでは「葬儀で流れた涙が多いほど死を惜しまれる、人徳の証」として、泣き屋を多く呼べる事は地位と人徳が高い名誉であるとされた。
昔、泣き屋を調べた時に見つけた「ある地方では葬式の日取りを風水で決めるため死んでから葬式まで数か月空く場合もあった。その際親族が泣くに泣けないのでプロの泣き屋を呼んで代わりに泣いてもらう」という事柄が印象的だったのだが、改めて調べても風水で葬式の日取りを決める地方がどこか不明だったのでこれの真偽は定かではない。
一説では泣き屋は儒教の儀式の中にある「哭礼」が元になっていると言われていたが、先に言ったように日本の神話には神から生まれた泣き屋という職業が描かれ、中東エジプトでは古代の壁画に泣き屋の姿が描かれている。儒教が成立する以前から存在が確認される泣き屋の歴史の長さと、弔いの文化への根深さが知れる。
死んだ後の魂の行方
死んだ後の魂の行方すら違う各国の死生観だが、故人と別れの言葉を交わす葬儀という場に「故人を思って泣きじゃくる存在」が必要とされた、という点は共通する所があるのだと気付く。同時に、名誉の証明であれ魂の浄化であれ、「故人よ悔いなく死を迎え、安らかであれ」と願う気持ちも共通するのだと感慨深くなる。
各国に現存する泣き屋が実際の葬儀の場で泣いている様子は調べると映像で視聴することができる。
一通り文献を漁って知識を得た後だと「これがプロの仕事風景」という斜に構えた考えが過ってしまうが、国ごとに違う・・あるいは文化や伝統に沿った泣き方、故人を悼む気持ちの表現の仕方に着目しながら実際に見比べてみるのも中々奥深いかもしれない。
※画像はイメージです。
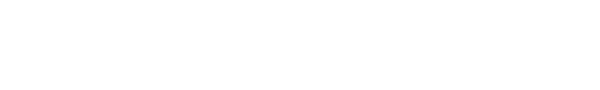


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!