もし、日本の幽霊界というのがあるのならば、一位になるのはお岩さんになるのは確実だとおもいます。
そんなお岩さんの実像ですが、四谷怪談で描かれているお岩さんとはかなり違っています。
お岩さんの本当の顔と、そしてお岩さんの祟りというものが、はたして本当にあるものなのでしょうか?
東海道四谷怪談のあらすじ
時は元禄。岡山藩の浪人民谷伊右衛門は、恋仲であったお岩との婚儀をお岩の父である、同心の左門に反故にされ、あげくのはて侮辱されてしまうという始末。
それでも、お岩に未練のある伊右衛門は左門に復縁を迫りますが、にべもなく断られてしまいます。
怨み骨髄にまで達した伊右衛門はある夜、ついに左門を切り殺してしまい、左門は御金蔵破りの犯人に殺されたのだと嘘をつき、仇を討とうと、お岩をつれ江戸へ出ることになります。
いつかは仇を討つ等とうそぶきながらも子供も生まれ、仲睦まじく暮らしていた2人でしたが、お岩は産後の肥立ちが悪く病気がちになってしまいます。
そんな時、あることがきっかけで助けた旗本の娘、お梅に惚れられた伊右衛門は、お岩がだんだんと疎ましくなり、お梅の父親が旗本であるという事実に色気づき、ついにはお岩との関係を清算しようと考え、よく効く薬だと称し、だまして毒薬を飲ませてしまうのです。
毒薬をのんだお岩の顔には、大きな腫瘍ができ、髪は抜け落ち醜い顔にかわってしまいました。
伊右衛門の裏切りを知ったお岩は、伊右衛門と娘、お梅に強い恨みを残し、苦しみながら死んでいったのです。
伊右衛門は死んだお岩を一枚の板に張り付けて川に流したのですが、お岩の執念は死んでからもなお、すさまじく、幽霊となってあらわれ、お梅と伊右衛門に復讐を果たします。
というのが、1959年に封切られた映画、東海道四谷怪談のおおまかなあらすじです。
たしかに日本を代表する幽霊なだけあって、とても怖い話です。
伊右衛門の人とは思えない非道な行いが、この復讐劇をさらに盛り上げている要因なのかもしれませんね。
お岩さんの実像
この、いわゆる四谷怪談とは江戸時代後期の歌舞伎の作者である鶴屋南北や、落語家の三遊亭円朝がつくった話が元になっています。怪談話と定番として何回も、映画や舞台、小説になっていて、その度に様々な改変が加えられているので、かなりの数の四谷怪談があります。
そんな四谷怪談ですが、何もないところから湧いてきた話ではありません。
お岩さんはもちろん、伊右衛門もちゃんと実在した人物だったのです。
お岩さんは実在していた武家の娘さんで、夫の伊右衛門とも仲睦まじく幸せにくらしていたそうです。
一時は落ちぶれて貧しい時もあったそうですが、お岩さんの献身的な働きと、屋敷内にあった社を信仰していたおかげで、再興をはたした。
と言う話が伝わっています。
お岩さんが信仰していた社は「お岩稲荷」と呼ばれ、現在でも四谷にある「四谷於岩稲荷田宮神社」で祀られているようです。
なぜ、怪談話になったのか?
実在していたお岩さんは、夫をたて、家までも再興させる良妻賢母の代表のような人です。それなのになぜ、こんな恐ろしい幽霊として描かれ、何百年もの間語り継がれてきたんでしょう。
四谷怪談の元ネタは残っています。
「於岩稲荷由来書上」という報告書。
これは江戸の各町に伝わる逸話や歴史などをまとめて報告した、四谷町方書状という書物のなかにある話です。
もう1つは「四谷雑談集」、元禄時代に起きた事件をまとめた書物です。
これらをまとめて、四谷怪談という1つの物語ができたのではと言われています。
四谷怪談ができるまでの経緯はなんとなくは理解できますが、それにしても良妻賢母のお岩がなぜ、その幽霊のモデルになったのかは、はっきり記されてはいません。
お岩さんがあまりにも良いイメージだからこそ、それをねたんで出来た話だという説もあるくらいです。
お岩さんの祟り
四谷怪談が創作であると、はっきりしているのになぜ、祟りがあるといわれているのでしょうか?
これには、意外とはっきりした根拠があります。
江戸時代、歌舞伎で「四谷怪談」の上演中に事故が相次いだことから、お岩さんの祟りに違いないという噂が広まりまし
た。いまでも、舞台や映画、ドラマでお岩さんのことを、取り上げる時は、お参りするというのは良く聞く話です。
怨み、祟りとはぜんぜん縁のない、1人の女性から日本を代表する幽霊をつくりあげるなんて、人間の創造力はすごいものがあるものだと、あらためて感心してしまいました。
なんだかんだ言いながら・・・今、この話を書いてしまった以上。
やはり、念のため「於岩稲荷」にお参りにいこうとそう思っています。
※画像はイメージです。
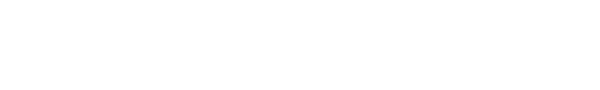


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!