きょうび、裁判といえばドラマや創作物でも描写が多く、万人がほぼ同じ光景を思い浮かべることができるだろう。では、現在の裁判の手順や方法が確立されるより前の時代。先人たちはどのような物差しをもって罪の有無を問うていたのか?
調べると中々に興味深い事柄を発見したので紙面を広げる。
裁判の制度が整備されるよりも遥か昔、人が人の罪の所在を神に問うた時代が存在した。
神明裁判
神明裁判とはその昔世界各地で実際に行われていた裁判方法で、裁く対象の善悪、罪の有無を神意に委ねた裁判である。神明裁判は各地に根付いた宗教の影響を大きく受け、また地方によって手順や内容に微妙な違いが見られる。
警察や検察、裁判所といった治安維持のための機関や組織が整備されていなかった当時ならではの「コイツが無罪か有罪か神に決めて頂こう」の発想で、中には理不尽な裁決法も多々あるが、神明裁判の記録は随所に残っており、我が国日本も例外ではない。
有名どころを掻い摘んで紹介していく。
中世ヨーロッパの神判
審判をキリスト教の聖職者が務め執り行われた。裁判を行う際、被告人に対し「この人間は嘘偽りなく証言する者である」とその人格を知人たち複数人で保証する雪冤宣誓(せつえんせんせい)が行われるが、それが成立しなかった場合に神判に移った。
神判はヨーロッパ各地でも方法が統一されてはおらず、
『被告人を水に沈めて浮かび上がってきたら有罪』
『熱した鉄の棒を握り火傷したら有罪』
『抽出した毒成分入りの水を飲み干して死ねば有罪』
など、どれも存外に理不尽な響きを醸している。
またヨーロッパの神判は雪冤宣誓不成立の他にも実行された事案があるが、これに関しては最後に後述する。
日本の神判
一章で記述した通り、神明裁判は我が国日本でも執り行われた形跡がある。古くは日本書紀に被告人の手を熱湯を張った釜に入れさせ火傷を負えば有罪とした『盟神探湯(くがたち)』の記録があり、後の中世…室町時代には『湯起請(ゆきしょう)』と名称を改め行われたようだ。
一見西洋の神判も日本の神判も「そんな決め方アリなのか」と眉間に皺が寄るが、よくよく文献を読み込んでみると盟神探湯は火傷するか否かではなく、目の前で1人の罪人が大火傷を負う姿を見せつけられた後続の罪人たち(無罪であれば臆することなく神判を受けようとし、有罪の者たちは火傷を怖れ狼狽える)その様子を見て罪の有無を選別していた。
西洋の『抽出した毒成分入りの水を飲み干して死ねば有罪』というのも、無罪の者が臆せず勢いよく飲み干せば毒は効かず、有罪の者が躊躇しながらゆっくり飲むと口内の粘膜から毒を十分に吸収し最悪死に至る・・・から・・・有罪という仕組みをしていた。神の意向に沿うと謳いつつも、ふたを開けてみれば意外と理にかなった選別法だったようだ。ではなぜ、このような暗に自白を促すような審判法が起用され、民衆に受け入れられたのか。
求められた神判
繰り返すようだが、神明裁判が活発に行われたのは起きた沙汰の真相を究明するための技術やそれを執り行う機関が未発達だった時代である。
主に被告人に雪冤宣誓で人格と証言に偽りなしと誓わせた上での供述しか罪を測る術が無かった。神明裁判は、その雪冤宣誓すら成り立たなかった場合に、ある種『沙汰の落としどころ』を見つけるために行われていた。
「被告人が被害者を殺したと物的に証明できない」
「しかし被告人の人柄も身の潔白を訴える供述も信憑性が無い」
「罪の所在が曖昧な現状、自分たちでは被告人を罪に問えないがそれでは被害者の関係者たちは納得しない」
「では」
「罪が果たしてどこにあるのか神に問うてみよう。神の決める事なら誰も異論は無いだろう」
といった具合に。
誰もが納得する、第三者的決定権を神が持つことになった背景には、技術面が発展途上かつ宗教が浸透した時代も影響しているだろうが、文献を見ていくと、先人たちが神意を何も盲目的に汲んでいたのではないとわかって中々興味深い。
もう一つの神明裁判
そして紙面が尽きるので走り書きになるが、ここまでで神明裁判に興味を持った読者諸君にもう1つ。
ヨーロッパでは神明裁判は雪冤宣誓不成立の他に、魔女裁判の際にも横行している。そう、魔女裁判だ。神判の内容、神判が必要とされた動機、これらを照らし合わせると勘のいい者は何かが見えてくるかもしれない。
深淵に足を浸す思いで調べてみるといい。
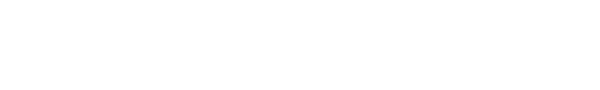


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!