それは僕が未だフルに働いていた少し前のことだ。ある時会社の同僚に、工藤さんは見えるんですか?と聞かれたのだ。僕は嘱託になり少し仕事にも余裕ができてきたので、僕の書いた都市伝説について、過去に少し話したことがあった。
それで、てっきり僕が見えるのではないか、と思って聞いてきたらしい。
「とんでもない、僕なんかには見えませんよ(鈍感だから)」と、最後の方は言葉を飲み込んで返答した。
「そうなんですか、私は何か怖い話ばかり書いておられるようなので、てっきり見える方だと思っていました。私の知り合いには、結構そういう人が多いのです。お母さんがそうなら、息子もそうだったり……」
「へぇー、僕はあっちこっち出歩いていますが、そういう人は知らなかったです」僕は話がオカルトの方に流れだしたので、内心ビリビリしていた。
小説とか、映画とか、コミックとか、要するにフィクションで鮮血がほとばしるとか、首がギロチンではねられるとか、顔の皮を剥ぐとか、は平気というか趣味なのだ。でも、現実の世界の僕は小心者だ。注射針を見るのも怖くて出来ないくらいで、採血された赤い血など到底見れない。目を横に逸らしたまま、ただただ過ぎ行く時間を待っている。
同僚はたんたんと話を続ける。まるでぼくの心など無関心のように。
「見える人は、憑かれたりも良くするらしいですよ。ああ、最近こういう話を聞きましたよ」と、かってに友達から聞いた話をしてくるのだ。その友達はまた彼の友達から聞いたはなしである。仮にY君としておこう。
Y君は小学校、中学校と一緒の幼友達がいたが、高校になって別の学校に行くと次第に疎遠になっていった。二人は走るのが好きで、中学の頃までは、近くの公園をよく何周もして競っていたのだ。
高校生になると、Y君は走ることよりも、勉強の方にどちらかというと、力を入れるようになっていった。Y君の友達は相変わらず記録を目指して走っていたが、ある時事故に会い両足に大怪我をおってしまった。一年経って歩けるようになったが、走りだすとどうやら足に無理がかかり「痛い、痛い」と、その場に崩れてしまうようだ。
Y君は幼馴染の他の友達からそのことを間接的に聞いていた。
でも、病院にお見舞いに行こうとは思っていたが、走ることに全青春をかけていた友達に、慰めの言葉が見つからず、ついつい延ばし延ばしにしていた。
そんな時、幼友達は絶望のあまり自殺してしまった。
お葬式があった。母は幼友達のことを悲しんで、一緒に行こうといったが、僕は行けなかった。それから2、3日たって母が買い物に行こうとした時、急に玄関で倒れる音がした。Y君はびっくりして玄関に駆けつけると、母が「痛い、痛い」と両足をさすり玄関に座り込んでいた。
「これは本当に彼のたたりかもしれない。小さい時はあんなに仲良くしていたのに――怪我した時、お前病院にも行かなかったから」と、迷信深い母は恨めしそうに言うのであった。
僕は本当は、彼が羨ましかったのだ――自分の好きなことに一生懸命になれた彼。僕は途中で挫折したのだ。社会という大海原に怯えて、こじんまりした未来にしがみついただけなのだ。
「◯◯君、ごめん。一緒に走れなくてごめん、病院に行けなくてごめん、お葬式に行けなくてごめん。でも◯◯君はずっと僕の友達だよ。だから、不義理は僕なんだ。たたるなら、お母さんじゃなくて僕にたたっておくれ」
僕は今まで貯めていた感情を一気に爆発させ、その場で泣き崩れてしまった。母はあっけにとられ、不思議なことに痛みも消えてしまった。
母と僕は、これからも彼のことを忘れないようにしていこうと誓った。お盆になると、彼の墓に一緒に参ることにしている。
聞いた話を小説風にしてみた。いかにもな話だ。そして、他にも同僚は話をしてくれたのだが、僕はうわの空で聞いていた。
よくある話は、よく起こる、ということだろう――“憑かれる”というのは、ごく当たり前の話なのだろうか?
特殊な、または強力な霊能力を持った人だけに起こる事なのだろうか?
それとも、人間の心理に潜む隠された部分なのだろうか。
人間は科学面では発展してきたが、精神的なその分野での解明はまだまだなされていないのだろう。ありきたりの意味不明な、またはありきたりの不思議な話の中に潜む真実は、本当のところ、どうなんだろうと思ってしまう。
そうして、ありきたりの化粧をした怪談話は、本当の真実をさらけ出しているような気がしてならないのだ。(実話と言ってるけど読者はきっとフィクションとか誇張が入っている前提で読んでいる)
かといって、僕は実話怪談を読むのが嫌いというか、苦手なのだ。そこにはやはり、作者の小説作法や規則を超えた何かが潜んでいる可能性を感じるからである。できれば、そういったものに近寄らないほうが人間安心して生きていけるのでないか。
でも、ついつい横目で……。

※画像はイメージです。

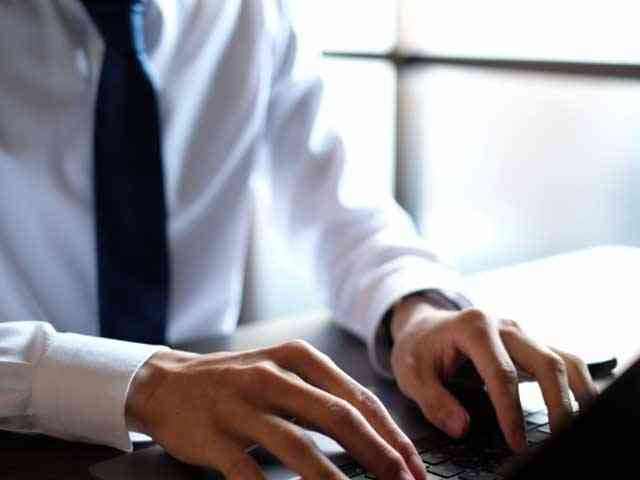

どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!