おおやけには、我が国の現代の首相や官僚や軍人や企業幹部や有名な運動選手や有名な歌手や俳優が歌を詠んだという話は、あまり訊きません。ただ、例外的に皇室の方々は詠まれています。
漢字を用いた難しい万葉仮名しかなかった古代において、天皇から庶民や一兵卒にいたる男女まで、心を打つような歌を残していることは、不思議としか言えません。それらの歌が記録されていることも奇跡です。これらのことについて考えてみました。
極端な例として、飛鳥から奈良時代にかけて詠まれたと思われる2つの歌をあげてみましょう。
持統天皇のお歌
春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香久山
政治的には平穏でなく苦渋なこともあったに違いない環境で詠まれたにもかかわらず、歌から受ける印象は非常に明るく庶民的なものです。季節の移ろいを、香久山の緑と干されている衣の白とを対比させて表し、衣替えという女性としての関心事に関係付けて、見事に表現しています。
現在の長野県(?)の一女性が恋人を想って詠んだ歌
信濃なる千曲の川の細石も君し踏みてば玉と拾はむ
この歌は、今から千年以上も前に一庶民が詠んだとは思えない歌です。大事な恋人が千曲川の浅瀬を渡って会いにきてくれたときに、その恋人が踏んだ小石ならば、玉と思って拾い大切に扱いましょうという意味でしょう。一流の歌人と呼ばれている人の歌にひけをとりません。
万葉集としてまとめられた歌たち
これらの歌は奈良時代に、大伴家持の編集によって万葉集としてまとめられました。大伴家持の先祖は、皇室が絶えそうになったとき、現在の福井県から後継ぎとなり得る人を継体天皇として朝廷に迎えることに貢献した大伴金村の子孫であり、大伴家持は庶民ではありません。大伴氏は分類すれば先祖は武門の家になりますが、家持は県知事のような職についていたこともあります。
万葉集は、西暦でいうと7世紀の始めから8世紀の後半にかけての間に詠まれた歌を、国が編纂したものとして集めたものです。律令国家としての形が整ってゆく時期にあたりますが、集められた歌の内容は、素朴で、率直で、全体的に国家的意図のようなものは感じません。これは、非常に不思議なことです。
海外における歌
海外において、このような例があるのだろうかと考えてみました。すぐ頭に浮かんだのは、唐詩選です。
唐詩選においては、唐の朝廷の高級官僚に分類される人達によって、うれいなども比較的率直に語られているすぐれた詩が、集められています。しかし、庶民が作った詩というのではないように思います。西洋では、どうでしょうか。西洋では、吟遊詩人ということばを、よく聞きます。
吟遊詩人は庶民に分類してもよいでしょう。しかし、断片的にそのような詩が残っているとしても、国家が関わった詩集の編纂というのは、聞いたことがありません。
結論として
これらのことから、以下の結論を出しました。つまり、日本人は、上から下まで全ての人が心の底では歌を愛していたので、自分の心を裏切ってまで率直な表現を損なうようなことは、自分の気持ちが許さなかったのではないかと。
そして、万葉集のような奇跡ともいえる歌集が生まれたのではないかと。
このことは、現在でも、和歌や俳句などを創る会が盛んなことで裏付けられていると思います。
※画像はイメージです。
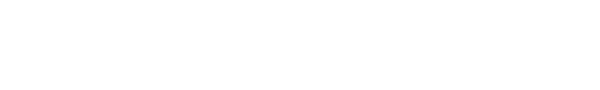


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!