トラック環礁は西太平洋カロリン諸島にある世界最大の環礁で、サンゴ礁に囲まれた広大なラグーン(礁湖)の周囲は約200Km。ラグーンの中には大小200以上の島があり、さらにラグーンの北部には空母が全力航行して離発艦の訓練を出来る広い海面があるところから、1942年から1944年2月まで日本の連合艦隊の大根拠地となっていた。
サンゴ礁に守られた広い礁湖内は敵潜水艦に襲撃される心配が無く、大艦隊の停泊や訓練にはもってこいであった。
帝国海軍のシンボルと化していた大和と武蔵
1942年8月7日、突然アメリカ軍はガダルカナル島に上陸を開始。予期せぬ早い反攻開始に、日本の連合艦隊も急遽山本五十六海軍大将座乗の戦艦大和を始めとする連合艦隊をトラックに進出させ、それ以後ガダルカナル島をめぐっての大消耗戦が始まった。
ガダルカナルの戦況が一進一退を続ける中、トラック泊地はガダルカナルへ向かう輸送船の中継地でもあり、また前線に出る艦隊の重要な補給基地となった。
しかし、多くの駆逐艦や巡洋艦がトラックを根城にガダルカナルへの兵員や物資の輸送そして敵艦隊との戦闘に明け暮れ消耗していく中、山本大将が座乗する旗艦大和は常にトラック泊地に留まったままであった。

By 日本語: 神田 武夫English: Hasuya Hirohata [Public domain], via Wikimedia Commons
武蔵はというと、1943年1月末に初めてトラックに入港、大和と並んで係留され連合艦隊司令部を大和から武蔵に移動している。その武蔵はブーゲンビルで戦死した山本大将の遺骨を乗せて5月18日にトラックを離れ、これもまた横須賀へ向かうのであるが再び8月にはトラックに戻る。そして10月の数日間の出撃を除いては翌1944年2月のトラック大空襲の寸前まで環礁内に停泊したままであった。
こうして見ると、大和と武蔵は1942年半ばから1944年初頭まで、まさにソロモン諸島での激戦が続いていた時期に全く戦闘に参加せず、数か月を除いてほとんどトラック環礁内にあったことになる。

By Japanese_battleship_Musashi.jpg:日本語: 白石 東平English: Tobei Shiraishiderivative work: 0607crp (Japanese_battleship_Musashi.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons
ある意味、大和・武蔵は帝国海軍のシンボル的な存在になってしまったとも言える。
大和と武蔵がなぜこのように動かぬ城になってしまったのか
それは開戦直前までの世界的な主流であった戦艦による大艦巨砲主義が、開戦後半年も経たないうちにもはや過去のものになっていたからであり、すでにこの二隻の超大型戦艦が実力を発揮できるような場所が無くなってしまったと言う事なのである。広大な洋上での艦隊決戦の主役はすでに航空機であり、現に行われているソロモン諸島での日米艦隊による激しい夜戦は、大和・武蔵の能力を発揮するにはあまりにも狭い海域で行われていた。
皮肉な事に、戦艦は航空機の攻撃にはほとんど無力だと言う事を証明したのが日本海軍による真珠湾攻撃だった。そしてそれを立案して実行したのが山本五十六大将であった。その教訓を素早く汲み取り実行に移したのがアメリカ軍であり、気が付かなかったのが日本海軍であった。それを痛いほど感じながら大和ホテルと武蔵御殿で過ごした山本大将の心境は、いったいどんなものだったのだろうか。

By USN ; Post-Work: User:W.wolny (U.S. National Park Service photo [1]) [Public domain], via Wikimedia Commons
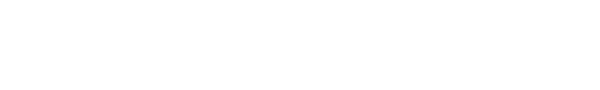


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!