太平洋戦争で文化財保護が目的で、米国が京都を空爆をしなかったという話をよく聞きます。
しかし当時の極秘記録が公開されてから、原爆投下予定地の一つだった事が判明してこれは真実ではない事が分かりました。
結果的には紆余曲折があって米国による破壊はごく僅かに止まったのですが、実は京都の街を最も大きく破壊したのは日本政府だったのです。
現在の大通り
五条通り、御池通り、堀川通りの3本の大通りは、現在、片側3~4車線の京都の大動脈として機能しています。五条通りは東京を起点とする国道1号線として、東から京都市街に入り、街のほぼ中央を横断して国道9号線となって西へ抜けています。
市街の北端から来る堀川通は、この五条通りと交差して南に超えると九条通りまで1号線として走ります。御池通りは鴨川沿いの川端通から西へ天神川まで走る通りですが、川端通・堀川通間だけが道幅が不自然に広くなっています。

強制疎開
戦争中の疎開は学童疎開がよく知られていますが、もう一つ建物疎開がありました。
これは空襲による火災の延焼防止目的の広幅防火帯を設置する為、街の指定区域の建物を撤去するもので、疎開指定は命令であり戦時中のこととて拒否は不可能なので強制疎開と呼ばれました。終戦までに全国で60万戸以上が撤去され、京都も例外ではありませんでした。
五条・御池両通りの南側、堀川通の西側に立っている家屋がその対象となって1万世帯以上が撤去され、元々幅員5m前後の道幅を50mに拡張しました。
戦後、この広い防火帯を利用して作られたのが上記大通りなのです。

実態
立ち退きが決定すると、発令から立ち退きまでの猶予は極めて短日時で、たった10日間程度で移転先を自ら探して立ち退かなければなりませんでした。
立ち退き補償は微々たるものでしたが、当時の日本では今の様な権利主張など望むべくもありません。
取り壊し作業は軍、廃材撤去は住民の勤労奉仕の分担でしたが、京都では中学校の生徒達などが大黒柱を綱で引っ張って取り壊しました。
「そこの家の人が泣きながら見てるから可哀そうやったけど、勤労報酬のかわりに廃材を持って帰っても良かったのがホンマは嬉しかったんや。物資不足で燃料がなかったさかいな。」とは当時取り壊しに参加したお爺さんの話。
現代では信じられない戦時中の日本の酷さや戦争の悲惨さを物語る話が、今たくさんの車が行きかう京都の大通りの下に埋もれています。
※画像はイメージです。
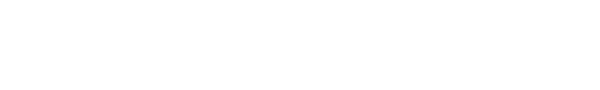


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!