太平洋戦争の海戦主力は航空機でしたが、その運用の仕方を詳しく調べると、日米両海軍の海戦に対する戦術の違いが見えてきます。
爆撃機と攻撃機

See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons
航空母艦には、零戦の様な艦上戦闘機の他に、艦上爆撃機(艦爆)と艦上攻撃機(艦攻)の機種が積まれていました。
戦闘機は、艦爆・艦攻及び空母の護衛が任務です。
敵艦船を攻撃するのは艦爆・艦攻でしたから、空母による海戦の際の主役はこの2機種でした。
艦爆は爆弾による爆撃、特に急降下爆撃を行う飛行機で、艦攻は魚雷による雷撃が役目でした。
また艦攻は大型爆弾の水平爆撃も行う事ができます。
映画の海戦場面でよく見るのは急降下爆撃ですが、命中率こそ高くなるものの実は急降下爆撃は大型艦船に対して撃沈する程の威力はありません。
戦艦・巡洋艦クラスでは装甲が厚くて、急降下爆撃による落下距離が短く小さな爆弾では貫通せず、 上部構造物の損傷のみで艦本体に対するダメージを与えられませんでした。
一方艦攻の魚雷は、喫水線下の装甲のない艦体部を破壊できるので、撃沈の可能性が高まります。
日米空母艦載機の比較

Japanese Media (1940s) [Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由
| 加賀 | 赤城 | エセックス・ヨークタウン級 | |
| 艦爆 | 24 | 18 | 36 |
| 艦攻 | 36 | 27 | 18 |
※単位は機
表を観てお分かりの様に、日米では艦爆と艦攻の搭載数が逆転しています。つまり日本の艦攻重視に対し、米国は艦爆を主力としています。
空母艦種や時期によってある程度変動はあるものの、概ねこの傾向は変わりません。
この差は、帝国海軍が敵艦船の撃沈を目指していたのに比べ、米海軍は損傷による一定期間の使用不能を目的にしていたからです。
この違いは国力の差から来るものと推測できます。
艦艇修理能力の高い米国に対しては、撃沈でなければ直ぐに前線復帰されてしまいます。
一方、米海軍は空母航空戦で最重要な早期発見早期攻撃を最優先しました。
重鈍な艦攻に比べ、小型軽量な艦爆の空母発進は短時間で済みます。
そしてとにかく、特に日本空母の甲板に穴を開けて一時的に使用不能にすれば、保有艦艇数や造船修理能力で優る自軍が優勢に戦える目算がありました。
敵艦隊は撃沈するべきものと考える帝国海軍と、小さなダメージでもよいからスピード重視で数多く損害を与えれば優位に立てる米海軍の戦術の違いが、両者の空母艦載機の運用から窺えます。
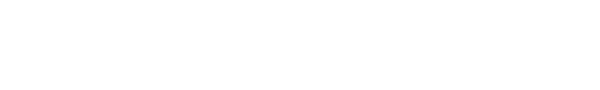




どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!