太平洋戦争において、人や物を運ぶ大部分を担ったのは輸送船となった船舶です。
日本はその大事な船舶をどう扱ったのでしょうか。
日本の輸送船の量
1941年(昭和16年)12月の太平洋戦争開戦時で、日本の船舶量は639万総トンありました。
この量は世界第3位の量です。
日本はこの中から陸軍用と海軍用に民間用と3つに分けて使用していました。陸軍と海軍は作戦や拠点への輸送に船舶を輸送船として使いました。
民間用船舶は占領した南方の資源地帯から、資源を日本本土へ運びました。
数では陸海軍390万総トンで、民間用は177総トン(その他72万総トン)と分けられました。
陸海軍が使用する量が多く割かれ、民間用は必要な数よりも減らされていました。
軍は作戦が終わった時に輸送船を民間用へ返す事で、民間用の不足を補おうとしました。
しかし、次の作戦へ引き続き使用されたり、戦闘での損失で返す事はあまり実現できませんでした。
バランスの崩壊
開戦時から船舶は軍用が優先して配分されていました。
そこへ占領地の拡大が日本船舶の量をより追い打ちをかけます。
東アジアから太平洋の西半分に及ぶ、広大な日本の勢力圏を維持するだけでも船は足りませんでした。
そんな状況で1942年(昭和17年)8月から始まったガダルカナル島攻防戦は陸軍用に使用していた船舶が10隻以上失われた。
この損失からより船舶を割り当ててほしいとする陸軍と、民間用船舶を減らしたくない政府が対立する事態になってしまう。
結局は民間用を減らして陸軍用を増やす事になりました。
これが常に不足していた民間用船舶での運べる資源が減る事になり、日本の国力に影響を与えます。
これは当時の総理である東条秀機でさえも、鋼材生産が減るので陸軍用船舶を増やす事は十分検討して欲しいと言うほどでした。
壊滅
軍用の船舶追加はその後も続きます。
これは米軍の反攻で戦力移動の必要と、船舶の損害が増えた為です。
日本本土の造船所では、作業や工事を簡易化させた戦時標準船を建造して損失した船舶を補おうとしていました。
しかし、民間用船舶による資源輸送の減少は戦時標準船の建造に影響を与えます。
鋼材の不足で簡略化された型では、船体の強度をより低下させた。
これに徴兵で技術のある工員の代わりとなる動員学徒などの初心者が建造作業に入った事で粗悪な船が多く作られてしまった。
そこへ米潜水艦による本格的な活動で日本の船舶は軍用も民間用も損失が増えるばかりとなりました。
果たして民間用を増やす、または減らさなければ日本の資源輸送は問題が無かったのか?
石油を運ぶ油槽船(タンカー)は開戦時47万総トンありました。
その内の20万総トンは海軍が使いました。
残る27万総トンで必要とされる年間300万トンの石油を南方資源地帯から日本本土へ運ばねばなりませんでした。
民間用に残された油槽船は近海航路で運行していた小型な船が多く、一度に多くの石油を運べる船は少なかった。
戦艦や空母以上に輸送船となる船舶の数は日本にとって命綱と言える存在だったのです。
※画像はイメージです。
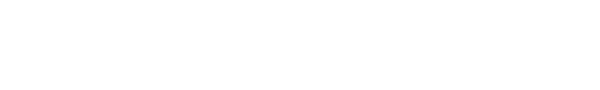


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!