現在の軍隊の兵士といえば、志願または徴兵により一般国民がなる事が当たり前です。
しかし幕末、戊辰戦争を始めあれほど戦争が起こった日本では、徴兵はありませんでした。
兵士はどう集められたのでしょう。
武士の職業

周知のように「士農工商」は江戸時代の身分制度で、「士」とは武士の事です。
職業で身分が別れていて、武士は政(まつりごと)と軍事を専らとする職業の身分だったわけです。
武士という身分の発生については諸説ありますが、概ね平安時代に起こったとされています。
以来、その役目の中心は武力の行使である戦争にありました。
明治維新と武士

強大な軍事力を背景にした欧米列強の侵略から日本をどう守るのかが、明治維新の最大の目的でした。
最終的に軍事力には軍事力で対抗するしかなく、幕末、軍事力とはそのまま武士の事でした。
長州征伐や戊辰戦争、長州対列強四か国(英・仏・蘭・米)との馬関戦争や、薩英戦争など幕末の戦争は当然武士が行っています。
明治新政府が発足した後でも、官軍は薩長土など諸藩の武士で成り立っています。
これら戦争の経験、特に対外戦争のそれから、大村益次郎など一部の軍事専門家は、武士だけで構成された軍隊では欧米列強に対抗するのは不可能な事に気付き、国民皆兵の必要性を感じていました。
徴兵令のもう一つの意味

そこで明治政府は身分にかかわらず兵士を募る徴兵令を定めます。
身分に関係がないというこの徴兵令は、取りも直さず軍事を専ら担う武士階級の否定を意味するものでした。
平安の世以来千年近くの長い間、存在して来た武士は、当時の日本人にとっては空気や水の如く当たり前なものでした。
特に武士たち当人には、武士以外の階級の人間が戦の中心になる事など、想像も理解もし得ない事だったに違いありません。
それは、例えば現代の日本で、逆に武士階級が復活して政治と自衛隊は武士階級の専門とする法律ができたとした時、私たちが感じる非常識感と同様です。
士農工商の身分制度のうち最高位の特権階級であり、最大の人口を閉めていた武士階級を廃止することになる徴兵令は、国の根幹を揺るがす明治維新の最大で最困難な日本改革だったと言えます。
そう考えていくと、明治維新が如何に難しい事業だったのか、その一端を感じる事ができます。
そしてこの徴兵令で集めた兵力を背景にして、廃藩置県というもう一つの大きな日本再構築が為されて行きます。
※写真はイメージです。
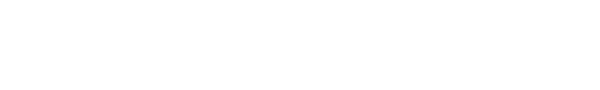


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!