竹刀を武器とする剣道がいくら強くても所詮、真剣を使わない只の棒振りダンスなどというのは暴言も甚だしいのです。
竹刀剣道と真剣剣術は違う
竹刀の重さは約4~500g、対して真剣は倍の1㎏以上にもなります。
だから振り回したり止めたりと、自在にこれらを扱うための体の使い方は全く違ってきます。
竹刀なら腕力だけで可能な動作も、真剣では足腰など体全体を使わねばなりません。
例えば竹刀剣道の技の一つ「小手打ち」は、手首を小さく使って打ち込みますが、重い真剣では振り抜くことしかできず、到底不可能な動きになります。
また面や胴も竹刀は打つだけですが、真剣では引くように刃を滑らせて切らねばならず、しかも刃が立っていなければなりません。つまり体の使い方は全く違ったものになり、竹刀剣道は真剣剣術とは似て非なるもので、実戦では役に立たないことも多いのです。
ところが剣術が盛んだった江戸時代後期、竹刀は実戦向けの稽古として発明され、それが現在の剣道のルーツとなりました。
木刀の形稽古
竹刀が登場する以前は、剣術の稽古は主に木刀によりました。木刀が実際に体の当たると骨折など大怪我になったり、最悪死に至ります。そのため木刀の稽古は形(かた)稽古でした。
つまり「相手がこう打ち込んできたら、こう受けて、返す刀でこう打ち返す」といった防御と攻撃の形がいくつもあり、その手順通りに遣り取りをするのです。反射的にその動作ができるまでこれを何度も繰り返し、体に覚え込ませます。打ち込みはもちろん「寸止め」です。
全ての武術においてこれは大切な基本なのですが、しかし相手がどう動くのか事前に分かっているのですから、この形稽古では相手の動きを読むとか、その動きに合わせて間合いを取るなどの実戦の駆け引きの稽古にはなりません。
実戦の勘を養うための竹刀稽古
実戦の勘を養うためには、実戦そのままに打ち合う稽古が必要で、寸止めもなく力加減もせずに、自由に打ち合う稽古のために竹刀が考案されました。
千葉周作の北辰一刀流が最高峰の剣術の一つになったのは、撃剣と称するこの竹刀稽古を重要視したからです。
古くからあった木刀の形稽古だけを中心とする剣術道場に比べ、千葉道場では門人の上達の早いことが人気を博しました。
それは基本となる木刀の形稽古と、実戦的な竹刀の撃剣を上手く組み合わせた結果でした。
まさに竹刀剣術は実戦向きだったのです。
参照:エンタメ剣道 剣道は、刀による実戦では通用しないのか
剣道の竹刀、その起源から今に至る進化の歴史
※画像はイメージです。
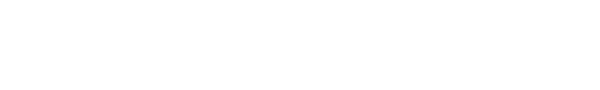


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!