日本陸軍の戦闘機と言えば一式戦闘機「隼」や三式戦闘機「飛燕」が有名ですが二式単座戦闘機「鍾馗(しょうき)」は先に挙げた機体と比べると知名度は低い。
どんな戦闘機なのかを紹介します。
重戦「鍾馗」
日本陸軍において戦闘機を区別する呼び方として軽戦と重戦があります。
これは翼面加重と呼ばれる主翼にかかる重さから軽いか重いかと判断しているのです。
日本陸軍は軽戦をクルクル動き回る格闘戦に強い戦闘機と位置付けています。一式戦闘機「隼」がこれです。

■一式戦一型乙(キ43-I乙)ないし丙(キ43-I丙)
Articseahorse [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

■ 三式戦闘機二型
Goshimini [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons
重戦闘機の役目を侵攻する敵機を迎え撃つ局地戦闘機と言う性格に固めます。
そうして作られた「鍾馗」は最高速度が600km/hを越える(Ⅱ型甲)戦闘機となった。同時期の戦闘機である零戦二一型よりも70km/h以上も「鍾馗」は速く重戦開発の目的は果たせたと言えます。
発揮でき無かった高速重戦闘機
「鍾馗」の正式採用は昭和17年(1942年)ですが実戦部隊はそれ以前から発足していました。
それが「かわせみ部隊」と言われる独立飛行第47中隊です。

■ 飛行第47戦隊の二式戦二型甲(キ44-II甲)
San Diego Air & Space Museum Archives [Public domain], via Wikimedia Commons
とはいえ正式採用前で量産もまだの戦闘機なので47中隊に配属された9機は全て試作機です。そこまでして開戦に備えたのです。
しかし47中隊が送られたインドシナやマレー半島では日本軍が進撃する作戦のせいか航続距離が短く局地戦闘機と目された「鍾馗」が活躍できる場は少なかった。
その後は米軍も600km/hを越えるP-51を投入すると「鍾馗」も速度では敵わず武装も12.7ミリ機銃が2丁または4丁とP-51よりも火力が弱く「鍾馗」は力不足にもなっていました。

■ P-51D
USAAF/361st FG Association (via Al Richards) [Public domain], via Wikimedia Commons
高い性能がありながらも活躍できなかったと見える「鍾馗」ですが日本陸軍が格闘戦重視で一撃離脱戦法こそ得意な「鍾馗」の性能を生かせなかったのかもしれません。
その証拠に「鍾馗」に乗り一撃離脱戦法で「赤鼻の撃墜王」と称された若松幸禧大尉が居ます。乗るパイロット次第で「鍾馗」は本当の名機となれた戦闘機だったのです。
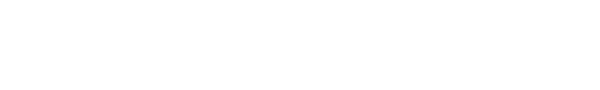


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!