「ストリテラ オモテとウラのRPG」は今年発売されたロールプレイ重視のシステム(ルールブックには「即興劇を遊ぶゲーム」と記載されている)です。
2面性があるキャラクターをプレイ
プレイヤーは表と裏、2面性があるキャラクターをプレイします。
例えば、オモテは「大人しい優等生」ですが、ウラは「世界の危機と戦う魔法少女」や、オモテは異性に興味がないスポーツ少年」、ウラは「とにかくモテたいと思っている」といった具合です。セッティングによってはウラが存在しない=表裏がないキャラクターを演じることもあるが、基本的に何かしらの2面性を持つキャラクターを演じることになります。
ロールプレイをすることに完全に特化したシステム
ストリテラのシナリオは基本的にオープニングチャプター、メインチャプター、ファイナルチャプターの3つで構成されています。
オープニングチャプターとファイナルチャプターは他のシステムと同様、大まかな流れが決まっているが、メインチャプターは決められた場面がいくつか用意されているだけで、展開はその場面に出るプレイヤーが即興でロールプレイを通して作っていきます。
どの場面にするかを選ぶのは、そのシーンの主役となるプレイヤー(「主演」と呼びます)です。メインチャプターではプレイヤーはひとり1回ずつ、主演としてメインチャプターに出られる。主演となるプレイヤーは他のプレイヤーを1人「助演」として指名し、そのプレイヤーと2人で場面を作っていきます。助演になれるのは1回だけです。つまりプレイヤーは主演と助演各1回、合計2回場面に出ることになります。
フラグポイントの獲得数を競う
ストリテラのシナリオのメインチャプターにはそれぞれ「キーワード」が設定されており、設定されたキーワードをキャラクターの台詞や行動に入れるなど、キーワードを織り込んだロールプレイをすると、得点(フラグポイント)がもらえます。またそれとは別にキャラクター固有のキーワードが与えられていることがあり、それを使ってもフラグポイントを獲得できます。
キーワードを使ってロールプレイを積み重ねてフラグポイントを稼ぎ、場面終了時に主演と助演、両者のフラグポイントの数を数え、多かった方が勝者となります。
こうして主演と助演各1回ずつシーンに登場し、勝利数が一番多かったプレイヤー(同点のプレイヤーが複数いる場合は獲得したフラグポイントが一番多かったプレイヤー)が物語にどの様な結末を与えるのかエンディングの方向性を決められます。
ロールプレイとストーリーを紡ぐことに特化したシステム
実は、「ストリテラ」はゲーム中サイコロを一切振らない。それどころか攻撃力や防御力といった、いわゆるステータスが存在しない。ただひたすら提示されたシチュエーションに合わせてロールプレイをし、即興で場面を紡ぎ上げていくのだ。ロールプレイをするためのシステムである。
ネタバレを気にしないで遊べる
通常、TRPGのシナリオはあらかじめストーリーの流れやダンジョンの部屋のモンスターや罠の配置が決まっている。配信を見てしまうとシナリオの内容はわかってしまう。ネタバレを気にする方も多い。 いくらそのシナリオが傑作でも話の展開を知ってしまっては、体験が変わってしまうからだ。
だが、本システムはメインチャプターの場面に応じたロールプレイを即興で行うという性質上、ネタバレが存在しない。せいぜい、どんな場面が用意されているかくらいだ。それもシチュエーションごとに導入こそ用意されているが、そこからどのように話が展開していくかは完全にプレイヤーに委ねられており、毎回話の展開が変わるから 、ネタバレのしようがない。
創作意欲を刺激する、キーワードを用いたセッティング説明
「ストリテラ」のルールブックに掲載されているシナリオは基本的にキーワード3つで説明されている。例えばルールブックに掲載されている魔王との決戦を控えた勇者たちの物語を描くファンタジー系シナリオ「勇者一行裏腹心中@魔王城」は「ファンタジー×決戦×因縁」、現代を舞台とした魔法少女の戦いと日常を描くシナリオ「フラジール・フレンドマギア」「現代×魔法少女×正体隠匿」といった具合だ。
いくつかのキーワードで企画の概要を説明するやり方はインターネット上の創作企画でよく行われている手法で、創作を主に行う層をターゲットにしているのだろう。
ロールプレイのやり取りを楽しみたい人に!
「ストリテラ」は数値管理するものがフラグポイントのみと、かなり簡単なものとなっている成功するかどうかわからない判定でハラハラしたり、カードゲームのコンボの様にデータを組み合わせて戦っていくことよりも、何よりもロールプレイで遊びたい人におすすめのシステムだ。
(C) 瀧里フユ/どらこにあん (C) KADOKAWA
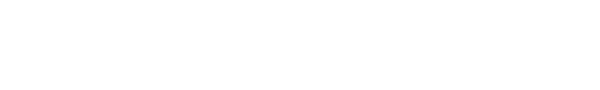



どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!