多くの兵士が死ぬ戦場で、中にはいくつもの激戦を繰り返し潜り抜けて生き残る兵士もいます。
どんな兵士が過酷な戦場を生き抜くのでしょうか考察してみます。
死に易い兵士のタイプ

戦闘で死に易い兵士にはいくつかのタイプがあるそうです。
大言壮語タイプ
常日頃、自分の勇敢さや強さを必要以上に誇示している者は、 それが為に戦場でも自らの言葉通り行動しようとして、無理・無謀をしがちである。
戦場でのそんな行動は死に直結する。
好奇心旺盛タイプ
敵情や地形など必要な情勢把握を越えて単なる好奇心から必要以上に周囲の状況を知ろうとするタイプは、それだけ敵に身を晒す危険が増える。
また、戦闘に関係のない、自分の嗜好に気を取られる事(例えば綺麗な花に見惚れるなど)も集中力を欠いて危険が増大する。
注意力散漫タイプ
いわゆるドジな人間。
戦場には危険回避の為に注意すべき事柄、禁止事項などが数多くある。
自分が所持する小火器自体に殺傷力があるだから、不用意に扱うと自身や仲間でさえも危険に晒す。
戦闘中は言わずもがなである。
例えば、夜間の奇襲攻撃の際に物音は厳禁である。そこでドジな奴は大きなクシャミをする。
それは自分だけでなく部隊全員を危機の陥れる。
臆病タイプ
臆病な人間は戦闘になると身体が強張って動きが鈍くなる。
また逃げることばかりに意識があるので、敵情を把握せず闇雲に動く為に敵の標的になり易い。
臆病者はその反面、慎重なのでは?と思う方もいるでしょうが、ここでの臆病は慎重が故に臆病と思われるというタイプではなく、完全な臆病者と考えてください。
でも結局は運

つまり死に易い兵士を反面教師にすれば、戦場で生き残る確率はアップするという事です。
しかし結局は運やツキが生き残る為に最も必要なものだとされます。
それは太平洋戦争の玉砕部隊の生き残り兵士や、戦後の近代戦を実際に経験した日本人が証言しています。
フランス外人部隊で、戦後にアフリカや東南アジアの戦争に参加したある日本人は、 自分の「勘」の善し悪しを知っておくことが生き残りの秘訣だと言っています。
戦闘に遭遇して瞬時に行動を起こすべき時、頼れるのは己の勘だけ。
自分の勘の的中率を確認し、常の生活の中でその向上を意識する事で勘が研ぎ澄まされ、それが生存率の向上に繋がるのです。
ゲームと違ってリセットのできない現実の死が訪れる実戦だからこそ、 理屈では捉えきれない何かを実戦経験者は感じ取るのでしょう。
参照 「戦場の人間学」柘久慶 著
※画像はイメージです。
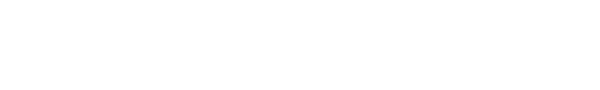


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!