数年前、若い男性のフードファイターの動画を見ていたら、ナイフとフォークの使い方が壊滅的でびっくりしました。
コメントでもギャグかよと笑いを取っていましたが、フードファイターさんはさすが関西人、これを逆手にとって「ワイの自慢のナイフさばきを見てくれ!」と、またステーキ早食いに挑戦してました。
そして、お肉の大食いの回を重ねるにつれてナイフとフォーク使いも自然と上手になって来ています。
高校時代に課外授業等でテーブルマナーを学ぶ機会があるので忘れちゃったのか?と思ったら、院卒インテリフードファイターと意外・・・どこの大学かと思ったら、旧帝大だったのには色々な意味でびっくりしましたけどね。
意外なテーブルマナー
ところで、お箸を使う日本人は、西洋式のナイフとフォークのマナーが難しいとか敷居が高いとか思いますよね。
ヨーロッパでこのマナーが定まったのは、意外にも19世紀になってからで、中世ヨーロッパではなんと手づかみで食べていたんです。
手づかみと言えば、両手を使ってむしゃむしゃ食べる原始人的なノリを考えますが、19世紀までナイフやフォークを使わずに食べていた理由は、キリスト教に「神様が与えてくださった手と指で、神様に与えられた食べ物をいただく」という価値観が根底にあったからだとか。この宗教的な考えから、ナイフやフォークやスプーンなどの道具を使うまでに至らなかったということです。
それにもマナーがある
そして手づかみには手づかみのマナーがあって、食事の前には必ず手を洗うとか、食事中に手で鼻を触ってはいけないとか、当たり前のことがマナーでした。尚、マナーの心得のある王侯貴族は、親指と人差し指と中指の3本の指を使って上品に食べるけど、一般庶民は、5本の指を使ってがつがつ食べると言われたそうです。
それに食器も陶器が主流になるまでは、木で出来た皿や固いパンを代わりにしていたということです。よっぽど固いパンだったらしくてスープを入れるだけでなく、スープを飲むときのスプーン代わりにも使われたとか。
貴族は肉汁やソースがしみ込んで柔らかくなったパンを食べず、庶民におさがりとして食べていたようです。
ナイフ、フォーク、スプーンのカトラリーも財産的なもので、食事に招待した家で用意するのではなくてゲストがマイカトラリーを大事に箱に入れて持参したものでした。
裕福な家に生まれた子供が、「銀のスプーンをくわえて生まれてきた」というのはここから来たということです。
小指を立てるのは?
それで小指をピンと立てるというのは共用の器に入った塩や香辛料を使うのに、きれいな指を使わなければいけないというマナーがあったので、小指をきれいにしておくためにピンと立てていた名残だということなんです。現代の串カツ屋さんの二度漬け禁止みたいなマナーですね。
とにかく手づかみでも指を使って上品に食べるやり方があるとか、キリスト教的な考えで手づかみで食べたとか、現代人にはちょっと衝撃でした。
今後は、コーヒーカップを持つ手の小指をピンと立てる人を見つけたら、キモいではなくて、前世は中世ヨーロッパ貴族なんだなあと感心することにしましたです。
※画像はイメージです。
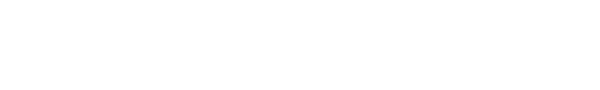


どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!